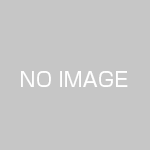抵当権の登記について質問です
仕事の関係で抵当権の登記事項と金銭消費貸借契約書を見比べることが多いのですが、登記されている利率と契約書に記載さている利率が異なるケースが多く見られます。素人が考えると登記と契約書の利率は同じのような気がするのですが…。いろいろ本を読みましたが、教科書どおりの解答は、「契約=登記」のようなのですが、実務ではどうも違うということなのでしょうか?ぜひこの利率の違いの理由を教えてください。ちなみに固定金利でも変動金利でも利率の異なるケースがありました。
まささん4719さん (島根県/36歳/男性)
まささん4719 さんこんにちは。
司法書士の小林です。
金銭消費貸借の場合についてお答えします。
ご覧になった記載を、『契約書 利息○○%』→『登記 利息△△%』と教えて頂けると推測できるかもしれませんがここでは、一般的にお話します。
お調べのとおり、原則は「契約=登記」です。
契約書には、固定であっても、変動であっても”契約時の利率”が記載してあり、それを登記します。
「いつからいつまでは○%、いつからいついつまでは△%」という契約で、その通り登記することもあります。
考えられるのは、
1) 契約と登記までの間に当事者の合意があって変更した
2) 契約書と登記の利率の記載方法が違う(%表示とそれ以外)
また、
>「抵当権設定契約証書には利息制限法所定の限度を超える利息の定めが記載されていても、利息制限法所定の利息に引き直して登記の申請があったときは受理される」(昭和29.7.13民事甲第1459号通達)<
という通達ほかがあります。引き直すというのは、200万円の元金に対して『利息 年30%』を『利息 年15%』として登記するということです。この場合は、契約書と登記の利息は異なります。(これは、登記できるかどうかで、現在、違法金利の契約に司法書士が関与することはありません)
などが考えられますね。