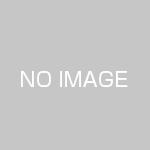いつの相続か、それが問題だ その1
私が最近扱っている案件で、被相続人が昭和55年に亡くなった、相続開始がだいぶ昔の登記案件があります。
ここでピーンときた方は相当な相続通ですね。
実は現行民法における法定相続分等は、昭和55年の改正法の施行(昭和56年1月1日)以降に開始した相続から適用されています。つまり昭和55年はちょうど境の年、現行民法の改正前の法定相続分で考えないといけません。ちなみに現行と改正前の法定相続分の違いは次のとおりです。
S23.1.1~S55.12.31
共同相続人
現行(S56.1.1~)
配偶者 1/3
子 2/3
配偶者と
子
配偶者 1/2
子 1/2
配偶者 1/2
直系尊属 1/2
配偶者と
直系尊属
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者 2/3
兄弟姉妹 1/3
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
昭和55年の改正法までは配偶者の相続分が少なかったのが特徴です。また現行民法では兄弟姉妹の孫以下に再代襲は認められていませんが昭和56年1月1日前に開始した相続では兄弟姉妹の子の直系卑属も代襲相続人です。
こんな知識も知っておくと役に立つかもしれませんね。
損をさせない 熱き心の司法書士 小林彰